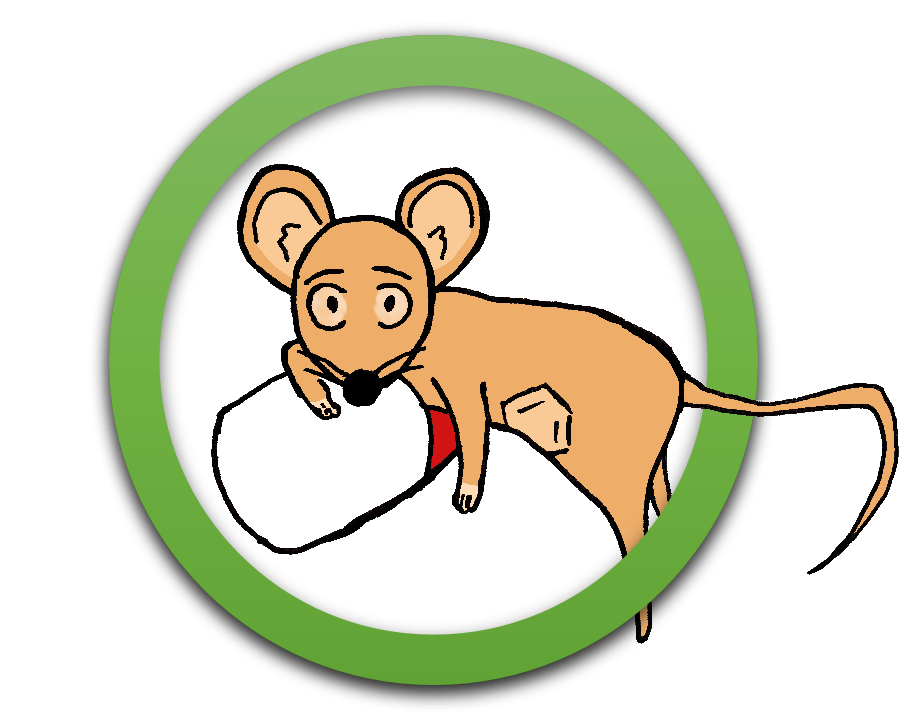※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
薬学生必見!中国医学の基礎を築いた三大古典を学ぼう 🎓【ごろ根っこの漢方日記】
薬学を学ぶ皆さん、東洋医学や漢方薬にも興味があるのではないでしょうか? 漢方薬の源流を探ると、古代中国で生まれた三大古典に行き着きます。これらは現代の東洋医学の基礎を築いた、まさに「バイブル」とも言える重要な文献群です。
今回は、その三大古典である『黄帝内経』、『神農本草経』、『傷寒雑病論』について、解説。

1. 医術の基本原理を説く:『黄帝内経』(こうていだいけい)
『黄帝内経』は、中国医学の理論的基盤を確立した最も古い医書とされています。編者や正確な成立時期は不明です。
📘 構成
この古典は、さらに『素問(そもん)』と『霊枢(れいすう)』の二部に分けられます。
- 『素問』 (基礎医学):宇宙観、自然との調和、陰陽五行説といった中国医学の基本的な理論や生理・病理、養生法などが記されています。いわば基礎医学にあたる部分です。
- 『霊枢』 (鍼灸):経絡(気の通り道)、臓腑、診断法、そして鍼灸(しんきゅう)の具体的な治療法について詳細に述べられています。
2. 薬物の効能を分類:『神農本草経』(しんのうほんぞうきょう)
『神農本草経』は、現存する中国最古の薬物書(本草書)です。編者は不明で、後漢時代には成立していたとされています。
🌿 薬物の分類
この書物の最大の特徴は、薬物をその毒性や薬効によって三つに分類した点です。全365種類の生薬が収載されています。
- 上品(じょうほん/上薬):120種。主に無毒で、長期服用が可能。生命を養い、不老長寿を目的とします。
- 中品(ちゅうほん/中薬):120種。毒性があるものとないものが混在。病気の予防や体力の回復を目的とします。
- 下品(げほん/下薬):125種。毒性が強いものが多く、主に病気の治療を目的とし、長期服用は避けるとされます。
3. 臨床医学の規範:『傷寒雑病論』(しょうかんざつびょうろん)
『傷寒雑病論』は、後漢末期の偉大な医学者、張仲景(ちょうちゅうけい)によってまとめられた臨床医学の規範となる書物です。彼は「医聖」とも称されます。
📑 構成と内容
この書物は、後に『傷寒論(しょうかんろん)』と『金匱要略(きんきようりゃく)』の二書に分かれて伝わることになります。
- 『傷寒論』 (急性熱性疾患):主に急性熱性疾患の治療法について記されています。病気の進行段階を「六病位(ろくびょうい)」に分類し、それぞれの段階に応じた治療法(方剤)を示しました。
- 『金匱要略』 (慢性疾患):**傷寒以外の様々な疾病**、主に慢性疾患(内科雑病)や婦人科疾患などについて論じています。
六病位の分類
| 病位 | 病期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 太陽病 | 陽病期(初期) | 風邪の初期など、体表の症状(悪寒、発熱) |
| 陽明病 | 陽病期(中期) | 胃腸に熱がこもるなど、実証の熱症 |
| 少陽病 | 陽病期(中期) | 寒熱が入り混じるなど、半表半裏の症候 |
| 太陰病 | 陰病期(慢性) | 脾胃の虚弱による腹痛、下痢など |
| 少陰病 | 陰病期(慢性) | 腎や心臓の機能低下、全身倦怠など |
| 厥陰病 | 陰病期(末期) | 寒熱錯雑など、病が深く複雑な状態 |
まとめ:三大古典から現代薬学へ
『黄帝内経』で人体の理論を学び、『神農本草経』で薬物知識を深め、『傷寒雑病論』で臨床応用を学ぶ。この三大古典は、薬学生の皆さんが漢方や東洋医学を理解するための最も重要なステップとなります。これらの知識は、将来、患者さんに漢方薬を提案したり、西洋薬との相互作用を考えたりする上で、きっと大きな力になるでしょう。😊 ぜひ、三大古典に触れて、薬学の幅を広げてください!